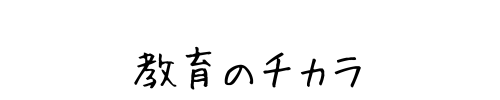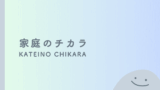今回の学習内容は、
- ① 繰り上がりのあるたし算の復習
- ② 繰り下がりのあるひき算
でした。今回は、②「繰り下がりのあるひき算」についてお話しします。
繰り下がりのあるひき算は、繰り上がりのあるたし算と並んで、1年生にとっての大きな山場です。
もちろんです。以下は、保護者向けにやさしく書いたブログ風の記事です。
タイトルや小見出しも付けていますので、そのままブログに掲載できます✨
🌸1年生の算数「繰り下がりのあるひき算」ってむずかしい?
1年生の算数も後半になると、いよいよ「繰り下がりのあるひき算」が始まります。
多くの子どもがここで少しつまずきやすい単元です。でも、仕組みをしっかり理解できれば、算数がぐんと楽しくなります。
今日は、家庭でサポートするときの大切なポイントをお伝えします。
🍎そもそも「繰り下がりのあるひき算」って?
たとえば
13 − 9 = ?
という問題。
一の位(3)から9は引けません。
そこで「10をかして」くるのが繰り下がりです。
つまり、「10のまとまりを1つもらってくる」考え方です。
この考えを数字だけで理解するのは、1年生には難しいもの。
だからこそ、具体的なもの(ブロックやおはじきなど)で体験するのが大切です。
🧮大切な2つのポイント
① 「10のまとまり」を理解している
繰り下がりのあるひき算では,「13」を見て,「10のまとまり」と「ばらばらの3こ」と具体的にイメージできることが大切です。それはこれまでブロックなどの実物をたくさん扱う体験を通して学んでいれば,ちゃんと育まれるものです。
② 「数を10と○」に分解できる
これまでもお伝えしてきた10を「2と8」のように2つに分けることに慣れていることが大切です。これができれば,「10から9をとる」というときに,すぐに「1」を出すことができるのです。
そのことを見通して,夏前から学校と家庭で取り組んできたたけちゃんです。
その力が通用するか,いつも通り、教科書を使いながら、学校の先取り学習を行ってみました。
🌰 「どんぐり」の問題に挑戦!
授業では、こんな問題に取り組みました。
「式は何だと思う?」
たけちゃんは、問題場面から正しい式を作ることができました。
💭 キャラクターのセリフから考える
教科書には、こんなキャラクターのセリフがあります。
このセリフの意味をたけちゃんにたずねてみると…
なるほど。子どもらしいすてきな発想です。
でも実はこのセリフ、「3からは9がとれないから、10から取る」という算数的な考え方を表しているんですね。
🧱 ブロックを使って、考えを深める
それをたけちゃんに気づいてもらうため、次のキャラクターのセリフ「どこから9をとろうかな」を使って、こう尋ねました。
「たけちゃん、どっちから9とればいいと思う?」
ブロックは2つのケースに分かれています。
- 10このまとまりのケース
- 3このケース
3このケースを見せて聞いてみました。
💬 たけちゃん:「とれない!」
「じゃあ、10のまとまりからなら9とれる?」
そして、10個のブロックから9を取りました。
💬 たけちゃん:「4!」
このようにブロックを使って質問すると、数字と実物を行き来しながら、自然としくみを理解することができます。
🧠 「わかった!」をしっかり定着させる
学校の授業では、先生の説明を黒板で見て終わり…となってしまうことも多いですが、それだと「なんとなくわかった」で終わってしまう子が多いのです。
だからこそ、もう一度似た問題で確かめることが大切です。
こうしてたけちゃんは、繰り下がりのあるひき算の考え方をしっかり理解することができました。
🍒 「さくらんぼ計算」で式の世界へ
ここまでで,具体物を通して,繰り下がりのあるひき算の考え方をしっかり理解したたけちゃん。次は,これを式だけでできる段階に連れていきます。
ここで登場するのが「さくらんぼ計算」🍒。
大切なのは、式と実物を行ったり来たりして考えること。
教科書の「さくらんぼ計算」を使いながら、たけちゃんがブロックでやったことの意味をもう一度確かめました。
たけちゃんは,「繰り上がりのあるたし算」に引き続き,最難関単元「繰り下がりのあるひき算」も本当にスムーズに学習することができました。授業と家庭学習の相乗効果で,これまでの積み上げがあったからですね。 これからも、たけちゃんと一緒に、ひとつひとつ丁寧に積み上げていきます。