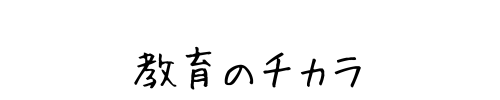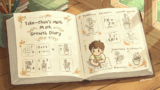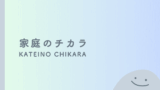9月30日の教育相談、最後のテーマは 「3つ口の計算」 の予習でした。
3つの数の計算って?
1年生の後半になると、いよいよ2つの数だけでなく、3つの数を扱う計算に進みます。
出てくるのは、大きく分けて3つのパターン。
① たし算 👉 2+3+4
② ひき算 👉 9-3-2
③ たし算とひき算 👉 7-2+3
ここのポイントは、
「たし算・ひき算は2つの数しかできない」
というこれまでのルールを、3つ以上にも応用できるルールに広げることです。
そして③のパターンでは、以前も出てきた 「演算決定力」 が必要です。
つまり、「ここは足す? それとも引く?」を、問題文や絵から自分で判断できる力です。
これまでは単元名が「たし算」だったら,何も考えなくても良かったけれど,③の場合は,たし算にするのか,ひき算にするのか場面から読み取って自分で決めなくてはいけません。そんな学習です。
まずはたし算から
先生:「この絵を見て、式を立ててみようか」
たけちゃん:スラスラっと「2+3+4」と式を書き、答えも正解!
たけちゃんの中で,「たし算は2つの数しか扱えない」と強く思っている様子はなかったです。式も答えもばっちりでした。
ひき算もクリア!
次に「9-3-2」のパターン。
これも迷わず正しく式を書き、答えまでスピーディー。
お母さんと一緒に続けてきた計算カードの成果がしっかり出ていました。✨
そして,たし算とひき算が混ざる問題
先生:「じゃあ、この絵から式を立ててみようか」
たけちゃん:「7-2+3!」
先生:「どうしてここは“たす”の?」
たけちゃん:「バスに乗ってくるから」
先生:「じゃあ、乗ってきたら数は増えるの?減るの?」
たけちゃん:「増える!」
このやりとりのように、理由を尋ねたり、「増える?減る?」とツッコミ(教育用語で“切り返し”といいます)を入れたりして、子供の説明で足りない部分をサポートしてあげることは大切です。このような経験を通して,「なぜそうなるか」 を考えることが思考習慣になっていきます。
15分で予習完了!
学校では3時間に分けて扱う内容を、たけちゃんは15分ほどでスムーズに終えました。
これまで丁寧にブロックやカードを使って数の概念を形成してきたからこそ、新しい学習にも自信を持って取り組めるのです。
これからのたけちゃんの歩みがますます楽しみになった時間でした。