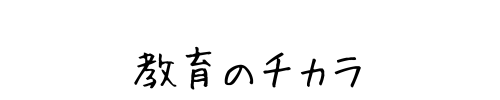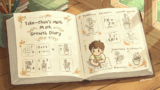9月30日の教育相談、2つ目のテーマは「数直線」でした。
今回はその様子をご紹介します。
○とびの数って何?
以前の記事で、たけちゃんが自分で○をつけた数の表を使いました。
0、5、10、15、20…といった“5とびの数”に○がついている表です。
先生:「たけちゃん、これは何とびの数かな?」
すると…たけちゃん、ちょっと困った顔。
実は「○とびの数」という言葉の意味が、まだピンときていないようでした。
大人には当たり前でも、子どもには未知のこと
算数には、子どもにとって聞きなれない“専門用語”が次々に出てきます。
「とびの数」もその一つ。
大人からすると「そんなの簡単でしょ?」と思いがちですが、子どもは初めて聞く言葉を一度で理解できるとは限りません。
ここで大事なのは、
「新しい言葉をすぐ理解できないのは普通のこと」
と受け止めてあげること。だってわれわれ大人でも同じでしょう。
それなのに,ついつい我々大人は,自分たちはできないのに,子供には「このくらい」と思ってしがちなのです。そういう癖があるということを知っておくだけで,子供への声掛けやサポートがずいぶん変わります。
0から5まで、どう数える?
先生:「じゃあ、指を0の場所に置いてみて。そこから5まで、何回とんだら着くかな?」
たけちゃんはしばらく考えて…「6!」と答えました。
これ、実はとてもよくある“つまずき”です。
0から数えてしまうために「0、1、2、3、4、5」で6回、と考えてしまうのです。
そのままにしておくと、時計の学習やものさしの目盛りを読むときに同じミスを繰り返すことになります。
一緒に指を動かしてみる
そこで私は、たけちゃんの指を持って一緒に動かしました。
「1、2、3、4、5」
先生:「何回とんだ?」
たけちゃん:「5回!」
先生:「そう!だからこれが“5とびの数”なんだよ」
たけちゃん:「あ~そういうことか!」
と、たけちゃんは思わずつぶやきました。前回も使っていた「5とびの数」という言葉の意味を理解した瞬間だったと思います。
少しずつ、自分の力で
その後は5とびの数を、今度は一人で数える練習。
次に2とびの数でもチャレンジして、しっかりと「2回とんでいる」と確認できました。
新しい言葉や概念は、大人が思っている以上に子どもには難しいもの。
でも、このように丁寧な支援を重ねれば、理解は必ず深まります。
次回は、いよいよ「3つの数のたし算」に挑戦するたけちゃんの姿をお伝えします!