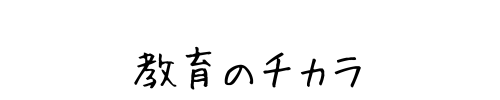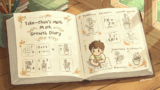【求差】を理解したたけちゃん
以前のブログで書きましたが,夏休み前のたけちゃんには「ひき算の【求差】(ちがいを求めるひき算)」につまずきが見られました。絵を見て,何となくひき算の式をたてることはできるのですが,その式になる理由については,少し曖昧な感じでした。
🍎 9月17日の教育相談より
そこで,教育相談の中で,改めて求差の理解度を調べてみました。
まずはこんな問題にチャレンジ。
「りんごが6こあります。みかんが4こあります。りんごは、みかんより何こ多いでしょうか?」
たけちゃんは迷わず「6-4」と式を立てられます。ブロックを並べて表すこともできます。
でも、そこで「-4をブロックで表してみて」と声をかけると…
「2しかひけない」とつぶやきます。
やはり,ブロックが図のように並んでいるとき,子供にとってなかなか「ひく4」をブロックで操作することは難しいようです。
✨ 声かけで変わる理解
「この2はどこ?」と尋ねると、ちゃんと多い2個のブロックを指差しました。答えの意味は分かっているのです。
そこで私は、
「このひく4は、りんごとみかんでセットになっているところだよ。セットで動かしてごらん」
と説明しました。
すると、セットでブロックを動かすことができました。
「これがひく4なんだよ」と教えます。
この段階のたけちゃんは,すっきり分かったわけではないと思います。ちがいを求める場合のひき算という新しい概念をブロックを通して理解しようとしている段階なので当然です。半分かり(半分わかった状態)でいいのです。
その後,他の求差の問題で,ブロックの操作の仕方を練習しました。
🍊 翌週(9月24日)の教育相談
同じ問題に再チャレンジ。
たけちゃんは、6個と4個を並べたあと、しっかりセットになった4個を動かして見せてくれました。
夏休み前には式と動きがつながっていなかったのに、今ではブロック操作と式を結びつけて考えられるようになったのです。大きな成長です!
学校の授業でもブロックを使う場面はありますが、1回の授業でサッとやって終わってしまうことも多いです。個々の理解度に合わせて、何度も丁寧に繰り返すのは、時間的にも難しいのが現実です。
だからこそ、こうして教育相談で一人ひとりに合わせた「オーダーメイドの支援」の効果の大きさをたけちゃんとの日々で痛感しています。