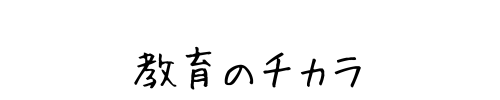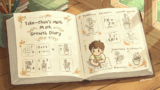「10より大きい数」にチャレンジ!
たけちゃんが学校の算数を少しでも自信をもって受けられるように、教育相談では予習も取り入れることになりました。今回のテーマは「10より大きい数」。
🌱 「10より大きい数」を学ぶってどういうこと?
小学校1年生の算数では、いよいよ 「10の次の世界」 に入ります。
「もうそんなこと習うの?」と驚かれる方もいるかもしれません。
でも実はここがとても大事なステップなんです。
子どもたちは、これまで「1〜10」をしっかり数えてきました。
その経験をもとに…
- 「10のあとには、11があるんだ!」
- 「12は、10と2でできているんだ!」
と気づくことが大切です。
🧩 ブロックや図でイメージをつかむ
そのために大切なことは,これまでと同じ,数と実物を関連付けることです。例えば「12」を学ぶときには、ブロックやイラストと関連付けます。ここでも教科書のイラストやブロックを数える際に,10個のまとまりと,はしたの2個にわけて数えることで,「12」という数の仕組みをより深く理解します。
また,数の大小や,並び方を学ぶ際にも,数だけでなく,数直線と関連付けることが大切です。「15と18、どっちが大きいかな?」と聞くと、数字だけで答えられる子もいると思いますが,数直線で確かめることも大切です。子どもたちは数直線を見ながら「18のほうが大きい!」と答えます。数の大小関係をつかむのに、とても役立ちます。
🍀 たけちゃんの様子
実際のたけちゃんは、「12を10と2に分けて考える」ことがとてもスムーズにできていました。
これは、夏休み前からご家庭で取り組んでいた「10のまとまりゲーム」の効果が出ているのだと思います。ご家庭での取組で,子供は大きく成長するんだなということを,改めて実感しました。
また,たけちゃんには,よく見られる十進位取り記数法のつまずきも見られませんでした。
✨ 十進位取り記数法とは?
「十進位取り記数法」とは,私たちが普段使っている数の表し方の仕組みのことです。
要点は2つです。
- 10ごとにくり上がる
1〜9まで数えたら次は「10」。さらに10が10こで「100」。 - 数字の場所(位)で意味が変わる
123なら、1は「100」、2は「20」、3は「3」というように、場所によって数字の大きさが決まります。
十進位取り記数法につまずきのある子供は,10と2個あるイラストを数字にする際に,「102」と書いてしまう場合があります。
でも、たけちゃんはここもバッチリ理解できていました。これは,教育相談での取組というより,たけちゃんのセンスだと思います!
次回は、数直線に挑戦します!