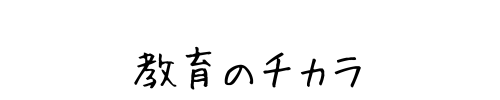8回目のたけちゃんの教育相談は,①○とびの数の復習 ②繰り上がりのあるたし算の復習
でした。今回は②繰り上がりのあるたし算の復習です。
✨ 宿題チェックからスタート!
前回、学校の予習としてはじめた「繰り上がりのあるたし算」。
最近、自信をつけてきたたけちゃんは、
「計算カードにチャレンジしたい!」
と自分から言っていたので、今回はそれを宿題にしていました。
宿題を見せてもらうと、
たけちゃんの集中力を考えて、
計算カードを3つほどに小分けにした**“ミニ計算カード”**を使って練習してくれていました。
これは本当に良い工夫です👏
😐 でも今日は…ちょっとやる気が出ない?
この日は、いつもより少し元気がなく、
計算カードを読む声もなんだかか細い感じ。
最初は自分でカードをめくっていましたが、
気乗りしない様子だったので、
私がカードを手に取り、**「一問ずつ出すスタイル」**にチェンジしました。
すると——少しずつ前向きに取り組みはじめてくれました😊
💡 たけちゃん、理解はバッチリ!
ただ,計算そのものは正しく答えることができています。今はゆっくり時間をかけていますが,それで大丈夫。仕組みはちゃんとわかっているわけなので,これから,練習量を積んで行けば,おのずと時間も短くなっていきます。
たけちゃんのように,まず仕組みが「わかった」上で,その次のステップで量をこなして「できる」ようにすることが大切です。
これまでも何度もお伝えしているように,「わかる」段階に至っていないのに,いたずらに量をふやしてもだめなのです。
🎲 思いがけない方向へ…
そんなことを思いながら,たけちゃんにたくさん計算問題をさせようと思っていたのですが。。。あまり気乗りがしない様子で,計算カードを仲間ごとに集めだしました。
観察してみると、
答えを見ながら同じ答えのカードを集めているようです。
最初は
「これだと同じ答えばかりになって練習にならないなぁ…」
と思いましたが、
「今日は気乗りもしていないし,このまま遊びながら,計算練習させよう」
と思いなおしました。
🗣️ 提案してみた一言
私:「こたえじゃなくて、式を見て、同じ答えになるカードを集めてみたら?」
「嫌がられたらどうしよう。」
と少しドキドキしながら提案しましたが、
たけちゃんは,幸い私の提案にのってくれました。(ほっとしました。。。)
そこで私は、仲間あつめしやすいように,1から20の数字のカードを出そうとしていたら,
たけちゃん、いきなりこう言いました。
「18は,1こね。」
思わずびっくり😳
「どうして?」と聞くと、
「いままで計算カードをやっていて、1つしかなかった」
と答えたのです。
ただ計算するだけでなく、
**「18になる組み合わせは1つしかない」**と気づいていた!
まさに算数のセンス✨
さらに、18が最大であることも理解していました。
📈 数の規則に気づく瞬間
そして次の発言にまた驚かされます。
「18が1こだから,17になるのは2こ,16になるのは3こじゃないかな。」
これは“覚えていた”というよりも、
数の規則性から予測を立てているということ。
これはもう立派な算数や数学で大切な考える力です👏
🔍 予想を確かめる探究タイム!
「じゃあ,実際にしらべてみようか。」
と声をかけると、
たけちゃんはどんどんカードを手に取り、
答えを求め、同じ答えの仲間を集めはじめました。
結果は——
なんと、たけちゃんの予想がすべて的中!
これには一緒にみていたお母さんも,私も本当に驚かされました。👏✨
🌈 “学び”は予定どおりじゃなくていい
本当は今日はドリルで計算練習をたくさん…と思っていましたが、
たけちゃんの様子を見て、計算カード仲間あつめに切り替えました。
でもこの活動の中で、
たけちゃんは予想 → 計算 → 検証という流れで
たくさんの計算練習をしていました。
それも、
「自分の予想を確かめたい!」
という自発的な目的のもとで。
🎯 教師としての学び
こんなにうまくいく日ばかりではありませんが、
子どもの表情や行動をよく見て、
その日の“最適な方法”に柔軟に切り替えること。
でも,目的は見失わないこと。
この2つをいつも大切に授業をしたいと思っています。
これからもたけちゃんと一緒に、
楽しく学びの時間を重ねていきたいと思います😊