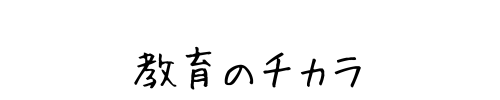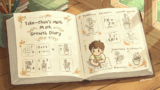教科書にこんな問題がありました。
□に入る数字を書きましょう。
-10-□-14-16-□-20-
たけちゃんは、最初の□に「11」と書きました。
どうしてだと思いますか?
「10の次だから11!」――子どもなら自然な反応ですよね。
でも、この□に入るのは「12」なんです。
この問題、実はとても難しいんです。
なぜなら「見えないもの」を考えなければならないから。
子どもがつまずく3つの壁
具体的にいうと,この問題を考えるためには,3つの壁があります。
- 14と16を見て,数字と数字の関係を見つけようと考えること
- 14と16の関係を見いだすこと(15が飛ばされている!)
- その関係が他の数字にも当てはまると考えられること
これまではブロックを使って「目で見えるもの」で考えてきた子どもたちにとって、数字だけの世界はとても抽象的でハードルが高いんです。
だからこそ、大人が「これがどれほど難しいことなのか」を理解して、子どもに寄り添うことが大切です。では,どうやってたけちゃんの「わかった!」を引き出せばよいでしょうか。
教科書には「かずのせんをみて考えましょう」と書かれています。
カギは「数直線」
ここで活躍するのが「数直線(かずのせん)」です。
算数の授業でよく出てくる「数直線」。
線の上に 0・1・2・3… と数字が並んでいる、あの図です。
「数字だけ分かればいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、数直線には大切な役割があります。
数の大きさや順番が“目で見て”分かる
小さい子どもにとって「17」と「19」のどちらが大きいか、頭の中だけで考えるのは難しいものです。
でも数直線を使えば、「19のほうが右にあるから大きい」と一目で分かります。
数を飛ばして数える練習にもつながる
「2とびで数える」「5とびで数える」など、かけ算や大きな数の土台になる学習にも役立ちます。
例えば,2とびの数は,かけ算の二の段,5とびの数は,五の段ですね。
足し算・引き算にも使える
「8+3」なら、数直線で「8から右に3進む」と表せます。
「12-5」なら、「12から左に5戻る」と表せます。
式がただの記号ではなく、“動き”として理解できるんです。
たけちゃんのひらめき
私はまず声をかけました。
「ここ(14と16)、見てごらん」
と声を掛け,14と16の関係を見るように声をかけました。どこを見れば良いのか分からない子供に考える手がかりを示すためです。考える手がかりを与えて考えさせるということは,非常に大切なポイントです。
それに対してたけちゃんは、パッと顔を輝かせて言いました。
「わかっちゃった!15を飛ばして16だ!なんか気づいた!17とばして,ここ18だ! 15を飛ばして16だから,17飛ばして18だ。だから19飛ばして20,21飛ばして22…31を飛ばして32か!」
自分で見つけた法則を、教科書の数直線に書き込んでいくたけちゃん。
つづいて,「0を飛ばして2、4、6、8、10、12…」と、今度は2とびの数を見つけ始めました。
さらに夢中になったたけちゃんはこう言いました。
「100まで書いてある表みたいなものがほしい!」
算数セットの中に「数の表」があったのでそれを渡すと、今度は5とびに挑戦。
夢中になって5とびの数に丸をつけていく姿は、とてもほほえましいものです。
自分の中で数の規則性が見えたために,もっと大きい数で試したいとたけちゃんは思ったのだと思います。これを周りの大人が「覚えなさい」と言ってしまうと,このような主体的な姿は引き出せません。このように自分でこだわりをもって追究することで,数の広がりの大きさを捉える経験にもなりました。
大人ができること
抽象度が高い問題だからこそ、
- 数直線を手がかりにすること
- 子どもが自分で追求し始めたら、黙って見守ること
この2つがとても大切ですね。
子どもが「自分で発見した!」と目を輝かせる瞬間は、算数の世界をぐんと広げてくれる大切な一歩。
そのきっかけを見逃さずに支えてあげたいですね。