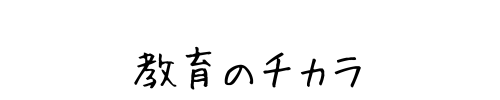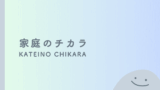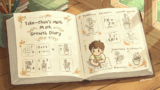最近のたけちゃんを見ていて,つくづく,「自信」って大切だなと思っています。
たけちゃんのお父さんもお母さんも,夏休み前からのたけちゃんの成長を実感してくださっているようで,お家でも,粘り強く考える姿がたくさん見られるみたいです。そして何よりうれしいのが,学校に楽しんで行くようになったそうです。
そんなたけちゃんの様子を見ていて,自分が一番したいことは子供に「自信」を与えるお手伝いなんじゃないかと思うようになりました。あくまで算数はそのきっかけ作りなのかもしれません。そんなことを,たけちゃんの姿や,ご家族のお話しから考えさせられる今日この頃です。
さて,「自信」をつける上で大切だと私が思っていることを今日は少しお話しさせていただきたいと思います。
それは,ずばり「評価」です。
「評価」って聞くと,みなさんは,どんなイメージをもつでしょうか。
ひょっとしたらネガティブなイメージをもたれるかもしれません。でも,じつは「評価」って「自信」をもつためにとっても大切だと思っています。
少し,専門的な話になりますが,評価には次の3種類があります。
🌱 3つの評価の考え方をやさしく解説
① 相対評価(集団の中で比べる評価)
イメージ:クラスの中で「順位」をつける感じ。
- 例)
かけ算テストで95点をとったAさん。
でもクラス平均が98点だったら、「がんばったのに上位ではない」という結果になることもあります。
ポイント
他の子と比べてどれくらいできているかを見る評価です。
② 絶対評価(決められた基準に達したかを見る評価)
イメージ:合格ラインが決まっていて、それを超えたらOKという感じ。
- 例)
「九九を正しく言える」など、目標がクリアできているかを見ます。
周りの子がどうかは関係ありません。
ポイント
“基準に達したかどうか”が明確なので、努力が結果に反映されやすい評価です。
③ 個人内評価(その子自身の中での成長を見る評価)
イメージ:昨日の自分、前の自分と比べてどれだけ伸びたかを見る感じ。
- 例)
前は「繰り上がりの足し算」が苦手だったけれど、最近は自分で練習して少しスムーズになった——これを前向きに評価します。
ポイント
“できるようになったこと”を見つけてあげやすい、子どもにとって一番身近な評価です。
みなさんは,どの評価が一番良い方法だと思われますか?実は,それぞれメリットとデメリットがあると思っています。
📊 メリット・デメリット
| 評価の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 相対評価 | ・競争心がわき、やる気につながることがある・学校全体での位置がわかる | ・他の子と比べて落ち込みやすい・努力しても周りのレベル次第で評価が変わる |
| 絶対評価 | ・目標が明確で、頑張りが結果につながりやすい・親が成績の理由を理解しやすい | ・「合格/不合格」的な面が強く、苦手が続くと自信を失いやすい |
| 個人内評価 | ・小さな進歩でもほめる材料になる・成長が実感しやすく、自信につながる | ・周囲との位置がわかりにくい・得意な子には刺激が弱いこともある |
🌈 子どもの自信を伸ばすための方法
結論から言うと、「個人内評価」がメインであるべきです。
「昨日の自分より成長する」ということが,私は人生の本質だと思います。その小さな積み重ねが,大きな成長につながるはずです。
でも,ご存知のように,残りの二つの評価が世の中にはあふれかえっています。大人の社会もそうですし,子供たちの学校という世界もそうです。理由は,見えやすいからですね。
では,学校で,周りの子供と比べたり,テストの点数が悪くて自信を失いがちが子供のために,私たち大人ができることを考えてみましょう。
① 日常の家庭学習は「個人内評価」を中心に
- 「昨日より速く読めたね」
- 「前は難しかったのに、今日できたね」
- 「自分で工夫できたね」
👉 小さな成長をたくさん見つけてあげると、子どもは自分の“伸びる力”を信じられるようになります。これは,家庭だからこそできることなんです。
比べるのは「昨日」でなくても「一か月前」でも「一年前」でも「小さい頃」でも構いません。それを保護者の方以上にできる人は世の中にはいないのです。
でも,「個人内評価」だけでは,自己満足に陥ってしまうこともあるでしょう。そのために,「絶対評価」と「相対評価」を上手に活用するのはどうでしょうか。
② 節目(テスト・通知表)は「絶対評価」で目標設定
- 「文章題を自分で読んで解けるようになろう」
- 「漢字テストで80点以上を目指そう」
👉 基準がはっきりしているので、努力の方向がブレにくくなります。
③ 相対評価は“刺激”として活用しつつ、心の負担は最小限に
- 「クラスで1番じゃなくてもいいけど、前よりもできることを増やしていこうね」
- 「あの子が速いからと言って焦らなくていいよ。ペースは人それぞれ」
👉 相対評価を“プレッシャー”にしない工夫が大切です。
🌟 最後に:自信を育てる黄金ルール
「比べる相手は、まず“昨日の自分”」
これを土台にしつつ、
絶対評価で目標を明確にし、相対評価は刺激として軽く添える。
このバランスが、
「自信」をもって取り組む子どもを育てる一番の近道だと思って,私は教育に携わってきました。
また,この原則はなにも子供だけでなく,大人も同じだと思っています。
「個人内評価」をベースとしながら,意識的に「絶対評価」として目標を決めて取り組み,自己満足に陥りそうになったら,世の中にいるもっとすごい人と自分を比べる「相対評価」で自分を鼓舞し成長を最大化する。大人になった時に,こんな風に自分で3つのものさしを使い分けられるようになれば,きっと素敵な人生になるのではないかと思っています。
私は教室で,こんな話を子供にしています。
子供が小さい内は,大人が積極的に「個人内評価」のサポートをしてあげて,段々それが自分自身でできるように促していくのもひとつの方法かもしれませんね。
長い話を最後までお読みくださり,ありがとうございました。では。