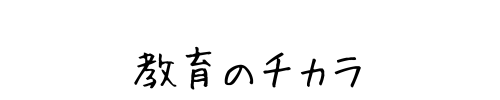「早く宿題やりなさい!」と言いたくなるときに考えたい、子育てスタイルの話
夕食のあと、子どもがテレビを見て笑っている。
親としては「先に宿題を終わらせてほしい」と思う瞬間、ありますよね。
つい「早く宿題やりなさい!」「なんで言われないとやらないの!」と強い口調で言ってしまう——。
そんなとき、私たちは知らず知らずのうちに「権威主義的スタイル(Authoritarian)」の関わり方をしているかもしれません。
🔹「権威主義的スタイル」とは?
子供との接し方に悩まれる方は多いと思います。一般的に,「子育てに正解はない」といわれ,それはある意味正しいのだと思いますが,それだと,我々は,考える手がかりや拠り所がなく,不安になります。
そんな中,心理学者のダイアナ・バウマリンドは、子育ての仕方を4つのスタイルに分類しました。
①権威的(Authoritative:民主型、バランス型とも)
②権威主義的(Authoritarian:独裁型、厳格型とも)
③寛容的(Permissive:消極型、甘やかし型とも)
➃放任的・無関心(Neglectful/Uninvolved:無関心型とも)
研究から,「①権威的スタイル」が最も望ましいスタイルであることを明らかにしたことは以前のブログでもお伝えしました。
今回は,①以外のスタイルがどうして課題が大きいのかもう少し深堀してみたいと思います。ダメな関わり方を知ることで,理想的な関わり方を考えていただければうれしいです。
今回は,「②権威主義的スタイル(Authoritarian)」。このスタイルは、
親が「厳しさ」や「しつけ」を重視し、子どもに強く指示する傾向があるスタイルです。
例えばこんな場面が典型です。
- 「理由はいいから、言われた通りにしなさい」
- 「口答えしないの!」
- 「決まりを守らないなら、遊びは禁止!」
このスタイルでは、親の言うことに従うことが最優先になります。
一方で、子どもの気持ちや意見を聞く機会が少なくなりがちです。
🔸このスタイルの何が問題なのか?
「厳しくすれば、しっかりした子になる」と思うかもしれません。
確かに、一時的には親の言うことをよく聞くように見えます。
しかし長い目で見ると、次のような課題が出てくることが研究からわかっています。
- ✅ 自分の意見を言いにくくなる
- ✅ 失敗を恐れて行動しにくくなる
- ✅ 人の顔色を気にしすぎる
- ✅ 自己肯定感が低くなりがち
家庭での会話が「命令」と「従う」の関係になってしまうと、
子どもは「どうせ言っても無駄」と感じ、自分の考えを話さなくなります。
これが、思春期以降の“親子のすれ違い”につながることも少なくありません。
🌱家庭でできるちょっとした工夫
――「権威的スタイル(Authoritative Parenting)」に近づくために
では、どうすればよいのでしょうか。
バウマリンドは、「権威的スタイル(Authoritative Parenting)」こそが、
最も子どもの自立と社会性を育むスタイルだと述べています。
このスタイルの特徴は、
「しっかりしたしつけ」と「あたたかい関わり」の両立です。
家庭でできるちょっとした工夫を、具体的に紹介します。
- ルールを一緒に考える
→「宿題はいつする?」「先にお風呂にする?」など、子どもの意見も取り入れましょう。
自分で決めたことは、責任をもって守りやすくなります。 - 理由を伝える
→「今のうちにやっておくと、寝る前がゆっくりできるよ」と、親の意図を説明することで、
“命令”ではなく“納得”の行動に変わります。 - 失敗を責めず、次に活かす
→「今日はできなかったけど、どうしたら明日はできるかな?」と一緒に考えましょう。
子どもは「挑戦しても大丈夫」という安心感を得ます。
💬おわりに
子育てに「完璧なスタイル」はありません。
大切なのは、日々の小さな場面で「子どもの声を聴こう」と意識すること。
その積み重ねが、**権威的スタイル(Authoritative Parenting)**に近づく第一歩になります。
今日の「早く宿題やりなさい!」を、
明日の「どうしたらスムーズにできるかな?」に変えてみませんか。