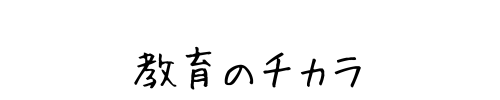前回に引き続き,たけちゃんのお母さまからいただいたご感想です。私は,特に「先取りやひたすら演習させようという焦りはなくなりました。」という言葉が印象に残っています。
多くの親御さんが「先取」をいいことだと考えてしまいます。しかし,その子供の発達段階にあった支援が最も重要なのです。少しばかり先に進んだからといって,必ずしもいい結果が出るわけではないことは,私たちは「うさぎとかめ」の童話でも学んできているはずです。
大切なのはその子供に合った学びです。たけちゃんのお母さまが気づかれた素晴らしい考え方を,少しでも多くの方と共有できれば,嬉しいです。
今までの家庭学習を振り返ると、子どもだけでなく、親にも“つまずき”があったことに気づきました。それは知識が足りず子どもとの関わりにすれ違いが生まれていたことです。
授業やブログを通して学び、特に参考になった点をまとめました。
📘① 深い理解に繋がる学び方
「速さ」「暗記」「正解・不正解を重視」など、気づけば私自身が算数を苦手意識を持った学び方を、同じように子どもにも求めていました。
先生の対話を大切にした授業の中で、たけが算数を楽しみながら考えるようになっていく姿を見て、
子どもの考えや意欲を引き出す関わり方の大切さを改めて実感しています。
🔍② 子どものつまずき
「1年生でよくあるつまずき(求差や抽象的な概念の難しさなど)」や「今の段階で必要な理解度」を親が知らないと、
子どもが分からない気持ちに寄り添えないことがあります。
授業やブログから、
“大人には当たり前でも、子どもには理解に時間がかかる概念”や、
“理解を深める過程”を知ることで、
以前よりも子どもの気持ちに近づけるようになりました。
🔗③ 学びのつながり
数の合成と分解が繰り上がりに繋がること、数直線が掛け算や関数に繋がっていくことなど、
学びのつながりを知ることで、親としても「今の学びを丁寧に積み重ねる大切さ」を実感しました。
そのおかげで、先取りやひたすら演習させようという焦りはなくなりました。
🍀9月後半の変化
先生との積み重ねのおかげで、たけは少しずつ数のイメージをつかめるようになってきました。
先取りはしていませんが、最近は繰り上がりに興味を持ち始め、
「まず10のまとまりを作る」ということに気づきました。
今まで練習してきた数の合成と分解が、新しい学びに繋がっていることを発見できて、とても嬉しそうでした。
1学期の頃は間違えることを嫌がり、学ぶことに消極的でしたが、
今は「もっと知りたい」「考えてみたい」という前向きな気持ちがどんどん生まれています。
算数の概念を“自分で考え、発見する楽しさ”として体験できたことが、たけの成長につながっているのだと感じています。
🙏感謝の気持ち
今までを振り返ると、自分たちだけでは到底辿り着けなかったことばかりで、
先生から学べる貴重な時間に改めて感謝しています。
いつも支えてくださってありがとうございます。