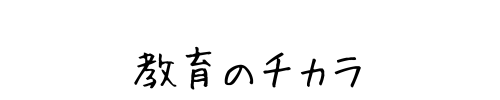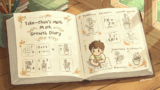計算カードの取り組み方
「先生、計算カードって、たくさんやらせたほうがいいんですよね?」
そんなご相談をいただくことがあります。
全国どこの小学校でも当たり前のように取り組まれている計算カードですが,その子供の状態によっては,害になることもあります。特に,数の概念が育っていない子供に,計算カードをたくさんさせることは,百害あって一利なし。こっそり指で計算したり,暗記しようとしたりするけれど,スピードも正確性も向上せずに,子供のやる気をどんどん削いでいくことになりかねません。
でも,計算カードも使いようによっては,数の概念を育てるツールになります。そこで,今日は数の概念を育てながら,無理なく計算カードとつきあうステップをご紹介します。
たけちゃんも、最初はただカードをめくって答えを書くだけでした。でも、このステップで取り組むことで、グングンと力がついてきています。たけちゃん公認の方法ですので,勉強につまずきのあるお子さんがおられるのであれば,是非ためしてみてください。
ステップ1:ブロックを見ながら
まずは「5-○」のように、最初の数ごとにまとめます。一日に扱うのは1つのシリーズでかまいません。焦らずにいきましょう。
例えば,「5-○」のシリーズの場合,5個のブロックを目の前に置きます。
ただし、ここでのルールは、ブロックには触らず “頭の中で動かす” こと。
これを「念頭操作」と呼びます。
実物と数字のつながりを頭でイメージできるようにすることが目的です。
ステップ2:ブロックなしで
次の段階は、ブロックを片付けてしまいます。
数字を見て、頭の中でブロックを出して,動かして答える練習です。
もし,困っているようであれば,ステップ1にもどってブロックを見せてあげてください。
ステップ3:まぜた計算カードで
この2つのステップに慣れてきたら、いよいよ混ぜた練習へ。
「5-○」に固定せず、いろいろな式を練習します。
ただし,計算カードを無理に全部させなくて大丈夫です。お子さんが負担に感じない程度の枚数に少なくした「ミニ計算カード」をつくるのがおすすめです。10枚程度なら集中できる子は「2-○」から「10-○」を1種類ずついれたセットを作ってすると良いです。もしくは,10枚セット,20枚セット,30枚セットのように3種類つくっておいて,毎日お子さんに選ばせるなんていうのも,いい工夫です。
計算カードにかかわらず,「選ぶ」という行為をさせることは,子供を主体的にするためにとても重要です。私の教育活動では,意図的にたくさん「選ぶ」という行為を取り入れます。ご家庭でもできるようなことはたくさんありますので,よかったら,是非挑戦してみてください。
たけちゃんは,現在ステップ3に入っています。夏休み前に比べて、ずいぶん速く、正確に答えられるようになってきました。何よりうれしいのは,たけちゃんが算数に自信を持ち始めていることです。
無理なく,正しいアプローチで子どもを支援すると,子供に自信をもたせることもできます。一人でも多くの子供の自信につながる取組を,これからも研究していきたいと思っています。
📌 親御さんへのポイント
計算カードは“量より質”。
実物と数字を結びつけるステップを踏むことで、子どもは自信をもって計算できるようになります。