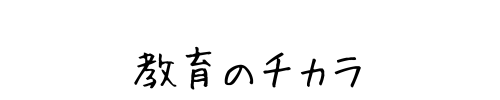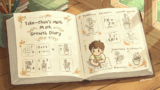前回の宿題では「ドットカード」を使って計算カードに取り組んでもらいました。
さて、次の教育相談の日――その成果を見せてもらうと…
「2-○」「3-○」「4-○」「5-○」まではスラスラ答えられるようになっていました✨
ところが「6-○」「7-○」「8-○」「9-○」になると、途端に時間がかかるんです。
不思議なつまずき
「6-○」シリーズを集中的にやってみると、さらに面白いことがわかりました。
「6-2」と「6-4」だけが時間がかかり、「6-5」や「6-1」は速く答えられるのです。
「どうしてだろう?」と原因を探ってみることにしました。
たけちゃんの頭の中をのぞいてみると…
「6-2」のカードを出すと、たけちゃんはしばらく考えて「4」と正解!
でもその直前に、小さな声で「3+1…」とつぶやいていることに気付きました。
そこで「どうやって考えたの?」と聞き、ブロックで表してもらいました。
すると――
たけちゃんは、次のように考えていたのです。
① ブロック上段の5個から2をとって「3」
② ①の「3」とブロック下段の1を合わせて「3+1=4」
なるほど!だから,ひき算なのに「3+1」とたし算をつぶやいていたのです。
一方,「6-5」や「6-1」が速かったのはなぜでしょうか。これもブロックのとり方に原因がありました。「6-5」はブロック上段の5をそのままとれるから,速かったのです。また,「6-1」はブロック下段の1をとるだけだから速かったのです。
こんな風に,子供の思考を丁寧にみていくと,その子なりのつまずき,分かり方が見えてくるものです。
効率的なやり方をプラス!
実はこの考え方、間違っていません。
むしろ,多様な考え方で,計算を考えるという発想は、数感覚を育てることにもつながります。
「数感覚」という言葉、保護者の方にとっては少し分かりにくいですよね。簡単に言うと――
👉 数感覚とは、「数を柔軟にとらえて、状況に応じて使いこなす力」のことです。
具体例をいくつかあげてみます。
例1:買い物でのおつり
100円玉を出して、70円のお菓子を買ったときに、
「100-70=30」と筆算しなくても、
「70に30を足せば100になるから、おつりは30円!」
とすぐに分かるのは、まさに数感覚です。
例2:暗算の工夫
「19+8」を計算するときに、
そのまま「19+8=27」と計算してもいいけれど、
「19を20にして、8を1減らして7にすれば…20+7=27!」
と考えるのも数感覚。
数を分けたりまとめたりして、計算を楽にする発想です。
例3:日常での気づき
お皿にリンゴが5個、もう1つのお皿に4個あるとき、
「5+4=9」と計算する前に、
「5と5で10だから、1個少なくて9だな」と気づける。
これも数感覚です。
筆算や九九といった「正確な計算力」だけでなく、
「工夫して考える力」や「数の全体像をつかむ力」があると、今後の算数につながっていきます。
言い換えれば、数感覚は“算数のセンス”を育てる基盤なんです。
たけちゃんの話に戻しましょう。たけちゃんの考えは,数感覚を育てる上では素晴らしい考えですが,しかし,今のたけちゃんは,ひき算の答えを出すために,たし算をするというこのアイディアを実行するためには時間がかかってしまうために,学校でのテストやプリントをするときなどに最後まで終わらないことがあったり,たし算をする過程で間違ってしまうことがあったりするのです。
そこで「速く計算したいときのコツ」を教えました。
「ブロックを動かすときには,5のまとまりになっていない方から取っていく」という方法です。
例えば「6-2」なら――
① ブロック下段から「1」を取る
② ブロック上段から残りの「1」を取る
→残りが4!
たけちゃんは,数のまとまりを認識しているため,4個のドット図をみてすぐ「4」と答えることができます。だからこの動かし方だと,速く処理することができるはずです。
大事にしたいのは,子供の考える力
一方,たけちゃんのアイディアも,素敵な考えです。むしろ画一的な方法で訓練するよりも,たけちゃんのように様々な考え方で計算しようとする姿勢は,数感覚を豊かにする行動で,今後の算数につながるため,その芽を摘みたくはありません。
だから今回は「速くやりたいときに使うワザ」として伝えました。
たけちゃんの「速く計算できるようになりたい!」という気持ちを後押しする形です😊
家庭学習の取り組み
お母さんとも話し合って、家庭学習では次の方針にしました。
- 「6-○」「7-○」「8-○」「9-○」を重点的に取り組む
- 今回学習した「速くやりたいときに使うワザ」でやってみる
さらに、たけちゃん本人にはこう伝えました。
「次の授業の最初に、計算カードがどれくらい速くできるようになったか見せてもらうね!」
次回、どんな変化を見せてくれるのか、とても楽しみです✨
📌 まとめ
ひき算が遅いのは「考え方が間違っているから」ではありません。
むしろ柔軟な発想をしているからこそ、時間がかかることもあるんです。
その子のアイディアを大切にしつつ、「効率的な方法」も教えることで、子供のやる気を損なうことなく,算数の力を伸ばしていきたいものですね。