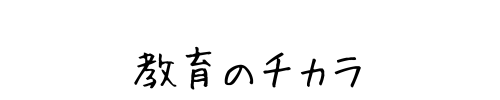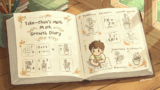さて,たけちゃんの演算決定力を調べてみました。
そのために,たし算の意味を理解しているかどうかを調べました。
たし算の2つの意味
たし算には,2つの意味があります。
①合わせる【合併】
「りんごが3個と2個あります。 あわせて何個?」
のように,ものをまとめるときのたし算。
②ふえる【増加】
「りんごが3個あって、お母さんが2個買ってきました。りんごは全部で何個?」
のように,あとから加わるときのたし算です。
大切なことは,2つです。
■問題文を読んで,合併,もしくは増加の場面であることが分かること。
■合併,増加の場面では,「たし算」を使うと分かることです。
理解度をチェックしてみた【合併】
問題文を読んで,たし算の場面かどうかを理解しているかどうか調べます。その方法は,問題文をブロックで再現させる方法です。
実際たけちゃんにやってもらいました。
まず,①合わせる【合併】です。

問題文「りんごが3個と2個あります。 あわせて何個?」とイラストを見せて,問題文と同じ数のブロックを出してもらいました。
次に,「あわせて何個?」の答えを,ブロックの動きで表してもらいます。
すると,たけちゃんは,3つのブロックと2つのブロックを
「がちゃん!」
と合わせました。また,式をたずねると,「3+2」と答えました。
このブロックの動きと,式が正しく言えることから,合併の場面については理解していることが分かりました。
理解度をチェックしてみた【増加】
次に,②ふえる【増加】です。
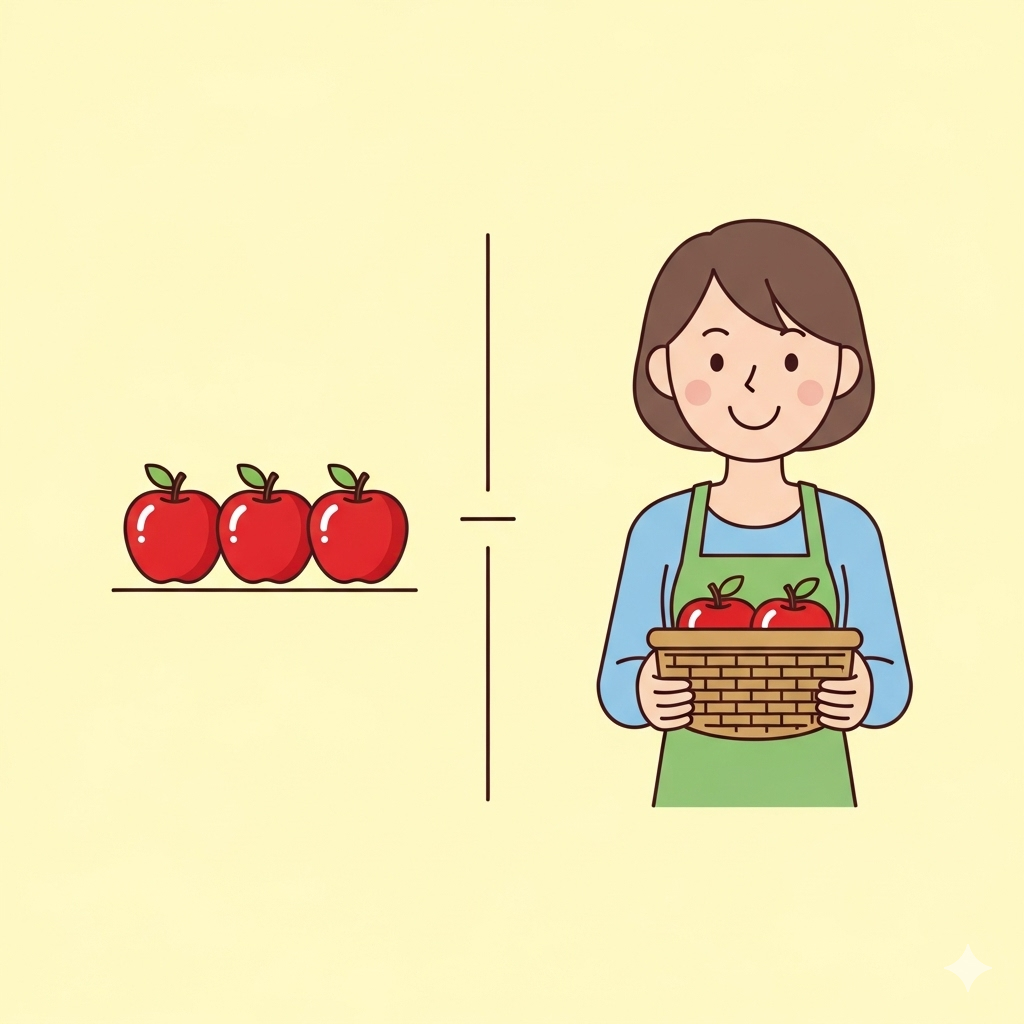
問題文「りんごが3個あって、お母さんが2個買ってきました。りんごは全部で何個?」とイラストを見せて,問題文と同じ数のブロックを出してもらいました。
次に,「全部で何個?」の答えを,ブロックの動きで表してもらいます。
すると,たけちゃんは,お母さんが後から買ってきた2つのブロックを動かし,元々あった3個のブロックにくっつけました。式も「3+2」と答えました。
このブロックの動きと,式が正しく言えることから,増加の場面についても理解していることが分かりました。
このように,ブロックの操作によって,子供のあまたの中で起こっていることを大人が把握し,子供の理解度やつまずいているポイントを見取ることが大切です。
たし算の2つの意味は理解していたたけちゃん,次回は,ひき算の理解度を調べます!