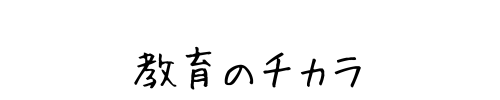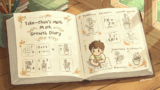次は,たけちゃんの演算決定力を調べました。
演算決定力
算数の文章題や問題を解くときには,「足すのかな?」「引くのかな?」「かけるのかな?」「わるのかな?」と,まずどの計算を使うかを決める必要があります。
この「どの計算を使うかを正しく選ぶ力」のことを,「演算決定力」と呼びます。
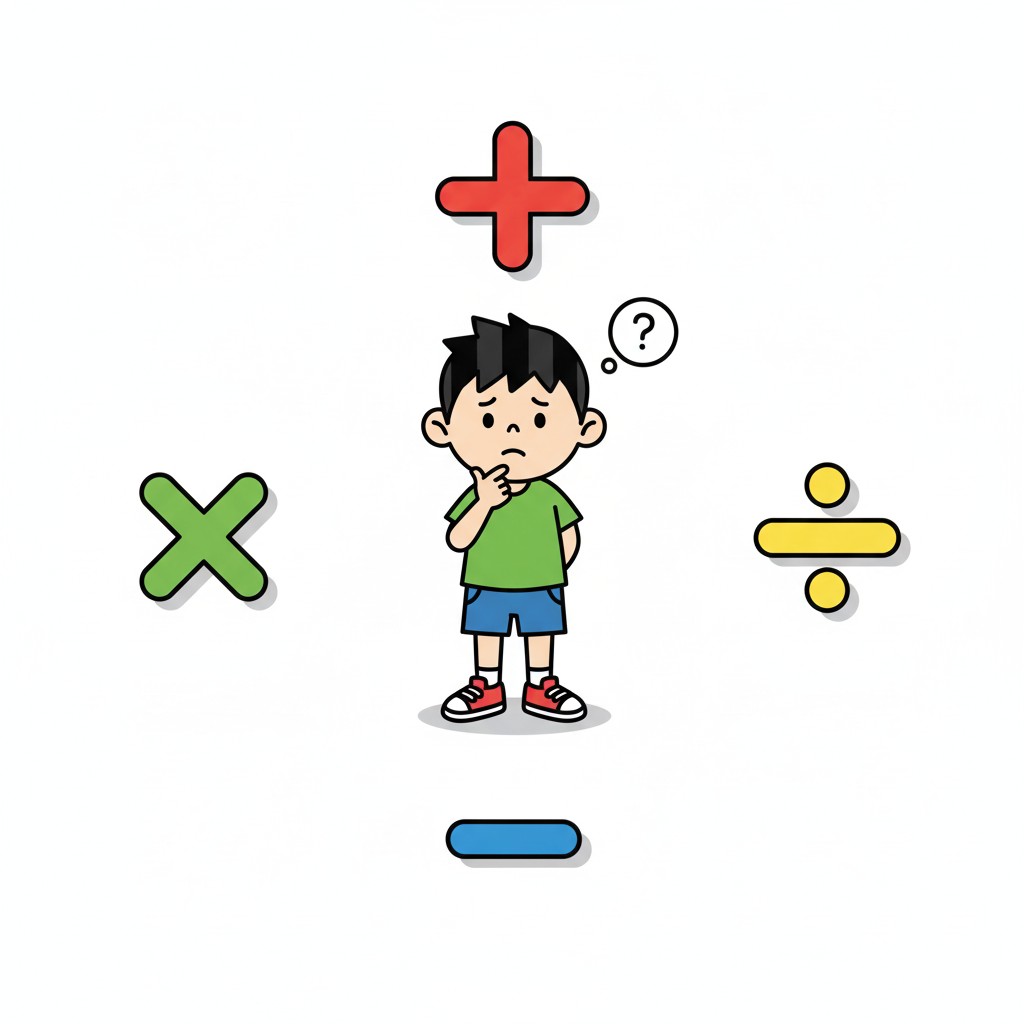
たとえば、
- 「りんごが3個あります。もう2個買いました。」→ 足し算を選ぶ。
- 「りんごが5個あります。2個食べました。」→ 引き算を選ぶ。
- 「りんごが3個入った袋が4つあります。」→ かけ算を選ぶ。
- 「りんごが12個あります。3人で同じ数ずつ分けます。」→ わり算を選ぶ。
このように、ただ計算ができるだけでなく、場面に合った計算方法を見つける力が「演算決定力」です。
算数の文章題では、ただ計算ができるだけではなく、「この場合は足すのかな?引くのかな?かけるのかな?わるのかな?」と、状況に合った計算の方法を選ぶことがとても大切です。
この「どの計算を選ぶか考える力」を育てると、次のような良いことがあります。
- 自分で考える力がつく
答えの出し方を先生や教科書に頼るのではなく、自分で「こう考えればいい」と見通しを持てるようになります。 - 文章題が得意になる
単純な計算練習だけでは文章題に強くなりません。状況を正しく読み取り、計算方法を選べるようになると、文章題にも自信がつきます。 - 将来の学びにつながる
中学校以降の数学や理科、さらには生活の中でも「どんな方法で解けばよいか」を考える力が役立ちます。
つまり演算決定力は、単なる計算の速さよりも、「考えて解く算数の力」を育てる土台になります。小学生のうちにしっかり身につけておくことが、算数を楽しく理解し、自信につなげるカギになるのです。
1年生の授業では,見落とされがち
こんなに大切な演算決定力ですが,算数の授業では見落とされがちです。
例えば,1年生の「たし算」の単元の教科書には,
「りんごが 3 こ あります。おかあさんが 2 こ かってきました。あわせて なんこ になりますか。」
という問題がありますが,たし算という単元名で,問題の中に出てくる数字も2つだけしかありません。これでは,子供は何も考えずに,2つの数をたすだけになってしまいます。
このような学習を1年生で続けていると,「演算決定力」が育たず,特に2年生後半からの算数の学習でのつまずきにつながります。
実際に調べてみた
たけちゃんは,1年生なので,「たし算」と「ひき算」のみ学習しています。そこで,この2つの演算決定力について,調べてみました。
次回は,たし算の演算決定力についてお伝えしますね!