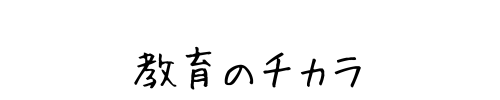🧩 7回目の教育相談、いよいよ挑戦!
たけちゃんの教育相談も、数えてみればもう7回目。
今回は、いよいよ1年生算数の山場——繰り上がりのあるたし算に挑戦です。
💬 結論から言うと…
たけちゃんは、あの夏休み前とは別人のようでした。
なんと、何も教えずにスラスラと正解を出したのです!この記事を読んでいただければ,くり上がりのあるたし算でお困りのお子さんを救う方法が見えるはずです!
最初に見せたのは、こんな問題。
たろうくんは どんぐりを9こ、
はなこさんは 4こ ひろいました。
あわせて なんこ ひろいましたか?
するとたけちゃんは、迷わず「13!」と答えました。
😲 正直、驚きました。
夏休み前まで指を使って数えていた子が、ここまで変容するのかと。
🧠 「どうやって考えたの?」を聞いてみた
もちろん、「正解!」で終わりではありません。
大切なのは、どう考えたのかを知ること。
私は、自作の教具を使って、たけちゃんの考えを“見える化”してもらいました。
🥚 ウズラの卵パックで「10のまとまり」を
使ったのは、ウズラの卵パックと紙粘土のボール。
このパックは10個で1セットなので、**「10のまとまり」**を自然に意識できます。
たけちゃんは、1つ目のパックに9個、2つ目に4個を入れました。
そこで聞きました。
「あたまのなかで,どう考えて13って考えたの?」
たけちゃんは1つボールを動かして10のまとまりを作りながら、こう言いました。
💬「10たす3で、あたまのなかの“計算くん”が計算して13ってわかる!」
といいました。「計算くん」っていう表現がいかにも1年生でかわいいですよね。たけちゃんが何を「計算くん」と表現したのかその真意はわかりませんが,10をつくることで,簡単にたし算できるという意味かもしれないと思いました。
🚧 繰り上がりのたし算にある「2つの壁」
繰り上がりのたし算は、1年生にとって最大の山場。
多くの子どもがここでつまずきます。
特に、「指で数える」やり方から抜け出せていない子は、要注意です。
理解には2つの壁があります。
🧩 第1の壁:「10のまとまり」の壁
繰り上がりのたし算では、まず 10のまとまりを理解することがポイントです。
たとえば、
8+5=?
→ 8と2で10をつくり、のこり3をたして13。
しかし、つまずく子は「8を10にするには2が必要」ということがよく分かっていません。
つまり、10をつくるイメージがもてないのです。
🧮 第2の壁:「数の分け方(分解)」の壁
もう一つの壁は、数を分けることです。
7+6 → 6を「3と3」に分けて
7+3=10 → 10+3=13
でも、実物と数が結びついていないと、「6を3と3に分ける」などが自由にできないのです。
子供を早い時期から数字だけの世界に連れて行ってしまった場合,子供は実物と数を関連付けることが十分できず,上の例のような場合に6を3と3にぱっと分けることができないのです。
🛠️ たけちゃんが“2つの壁”を越えた理由
第1の壁を越えるために、
ご家庭ではお風呂タイムにマグネットで「10のまとまり」ゲームを実践してもらいました。
第2の壁には、
ドットカードを使った3ステップ練習で、数と実物を関連づけました。
夏休み前は、時々こっそり指を使っていた,たけちゃん。夏休み前のたけちゃんは,時にこっそり指を使いながら計算をしていました。それは,数と実物が関連付いていないサインです。そこで,ドットカードを使い,3つのステップで計算カードをすることで,少しずつ数と実物が関連付いていったのです。
どちらも過去の記事で詳しくご紹介していますので,そちらをお読みいただけると,詳しい活動内容がよりお分かりいただけると思います。
🌈 「積み上げる学び」は本当に力になる
「算数は積み上げが大切」——よく聞く言葉です。
私自身も、講師として多くの先生方にお伝えしてきました。
けれど、たけちゃんの姿を見て、改めてその大切さを実感しています。
「正しく」積み上げることが、子供の笑顔につながる。
今回の出来事は、そのことを強く感じさせてくれました。