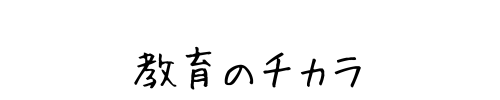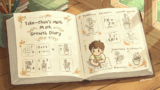みなさん、以前の記事で,「演算決定力」という言葉をご紹介しました。
ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、算数を学んでいくうえでとても大切な力なんです。
🧩 「たし算だけしてればいい」時期は終わる
この演算決定力,2年生の終わりまでは,あまり意識することがありません。なぜならば,「たし算」を学ぶ単元では,ずっとたし算をすればいいからです。数字も2つしか出てこないので、子どもたちは「出てきた数を足せば○がもらえる!」という経験を積んでいきます。
でも――2年生の後半になると状況が変わります。
同じ文章題でも「たし算かな?ひき算かな?」を読み取らなければならなくなるのです。
さらに学年が進むと、小数や割合の学習で「小さい数 ÷ 大きい数」という場面が出てきて、「割り算は大きい数 ÷ 小さい数でしょ?」と思い込んでいる子は,大混乱します。こうして子供たちの算数嫌いが加速していきます。
だからこそ、1年生のうちから「問題文を読んで、式を考える」という習慣を少しずつ育てていくことが大切なんです。
🍎 たけちゃんとのやりとり
今回は、教科書のイラストを使ってこんなやりとりをしました。
準備するものは,教科書のコピー。イラストと式をはさみで切って,たけちゃんと次のようなやりとりをしました。
「たし算になるお話はどっちだと思う?」
「こっち!」
「どうして?」
「だってこっちは逃げてるけど、こっちは来てるから」
「じゃあ、それに合う式はどっち?」
「これかな」
「どうしてそう思うの?」
「2匹のところに5匹飛んできたから」
――このやりとりの中で特に大事なのは、「どうしてそう思うの?」という「理由」を尋ねることです。
💡 「理由」を話す習慣が未来を変える
算数は「答えが一つ」と思われがちですが、大事なのは「どう考えてそう答えたか」。考えることを通して身に付けた知識や技能と,意味も分からずに覚えこんだ知識や技能とでは,大きな違いがあります。
理由を説明する習慣があるかどうかで、理解の深さは大きく変わります。
全国学力調査でも毎年指摘されていますが、多くの子が「理由を説明すること」が苦手なんです。それは,子供の能力ではないです。理由を説明する機会がなく,そのように頭を働かせる習慣が少ないからです。ただ,これって子供だけでなく,大人でもたくさんおられます。だからこそ、1年生のうちから「理由を説明する」ことは,今後の子供の成長のためにとても重要です。それは算数に限った話ではなく,これからの社会において,どの分野でも必要となることだからです。
🎲 ご家庭でできる!おすすめアイテム
「でも、教科書のイラストをコピーして切り取るのは大変…」
そんな親御さんにおすすめなのが 「文章問題かるた」。
文章カードとイラストカードを組み合わせるゲーム感覚で、問題文をよく読み、根拠を持って選ぶ練習ができます。
これが、これからの算数で必要になる「演算決定力」のタネになるのです。
たけちゃんも、このかるたを使って楽しく「たし算」「ひき算」を見分ける力を磨いています。
✨ まとめ
・低学年のうちから「理由を説明する」習慣をつけることが大切
・ゲーム感覚で学べる「文章問題かるた」はおすすめ
・理由を説明する力は、算数だけでなく,将来に役立つ力
今日のお話が、何かのヒントになれば嬉しいです。